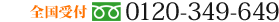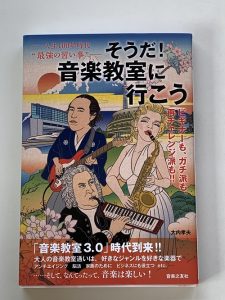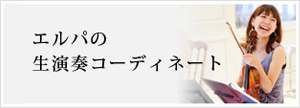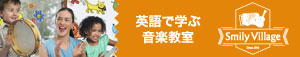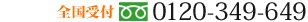こんにちは!
ブログでもご紹介させていただいた「そうだ! 音楽教室に行こう」の著者である大内孝夫先生にコラムを書いていただくことになりました。
全3回のシリーズ 第1回目は「小4の壁」です。
このコラムを読むと、壁の先の景色が見えてきます。
大内孝夫先生コラム①
「小4の壁」って 聞いたことありますか?
「受験とピアノなどのレッスンは両立しないもの」
と決めつけて受験を前にレッスンを辞めてしまう生徒が多くいます。
ピアノ教育では「小4の壁」という言葉があるくらいで、小学4年生になると受験勉強一本に絞るご家庭も多いです。
でも、私はこれがとてももったいなく感じています。
というのも、著名な音楽教室の先生に取材してみると、まるで口を揃えたかのように
「受験での中断期間が短い生徒ほど受験の成果は高い」とおっしゃるからです。
なぜでしょう?
お医者さんに話をうかがうと、人間の脳の集中力は意外と短いものなのだとか。
中には15分という説もあるほどです。
私の個人的感覚では著書など文章を書く際は1時間半くらいは集中できますが、
小さい頃は5分ともたず(笑)
小学校高学年や中学生時代には45分の授業が長く感じましたから、30分くらいだった気がします。
いずれにせよ、
一定時間を過ぎると脳は集中力を失い学習効果は大きく後退します。
集中力を失った脳は休ませることで機能回復しますが、
それでも国算社理、とか英数国理社と同じように机に向かって鉛筆を動かす勉強を続けていれば、
効率はどんどん落ちていきます。
そこにうまくピアノなどを取り入れれば、
手指を早く動かしたり、
音楽表現で体を揺り動かしたりするので、
脳の別の機能を刺激し適度な運動にもなります。
5時間、6時間と缶詰になって受験勉強するよりも、
いい気分転換になり受験勉強の密度も濃くなります。
そう考えると、先生方のお話にも納得がいきます。
脳は楽しいことや達成感を感じるとドーパミンという快楽物資を分泌します。
教えるのが上手な先生は技術だけではなく音楽の楽しさや喜びも教えていますから、
生徒をピアノ好きにします。
そのような生徒にとっては、
「この問題が解ければピアノが弾ける!」というのは、
ドーパミン分泌のもとになり集中力アップにもつながっていると考えられます。
私たちは「時間」にばかり目を奪われ、受験勉強と楽器演奏は相容れないものと捉えがちですが、
脳の「効率性」を考えると違う世界が開けていると言えるでしょう。
受験が近づいてきたら、毎週のレッスンを月1回にしたり、
受験半年前には一旦中断したりと工夫することで、
勉強も演奏も更なる高みに挑戦されてはいかがでしょうか。
「そうだ! 音楽教室に行こう」著者:大内孝夫
https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=212320